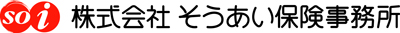『小金井通信』Dシリーズ 2025年10月 ◆「週刊保険情報」2017年3月
【アーカイブ】「週刊保険情報」2017年3月
酒井克彦中央大学商学部教授に聞く
〈プロフィール〉国税庁出身。中央大学商学部教授。大学では、税務会計論及び租税法を担当。中央大学ロースクール、中央大学大学院、税務大学校で教鞭を取る傍ら、税理士や公認会計士に対する啓蒙活動を行うアコード租税総合研究所所長やファルクラム代表理事を務める。1963年2月東京都生まれ。中央大学大学院法学研究科博士後期課程修了。法学博士。
生保税務の包含するリスクに対応するため、生命保険開発者ないし販売者から関心の高い具体的な事例形式で提示し、この回答を考えるスタイルを採用した画期的なテキストと言える『クローズアップ保険税務生命保険編』(編著・監修、財経詳報社)をこのほど上梓した、酒井克彦中央大学商学部教授は「租税専門家たる税理士は実務上保険税務に通暁していなければならない。そうでなければ納税者に応える税務処理はできない。保険税務が法人税法、所得税法、相続税法に横断的に関わりを持ち、税務実務上、極めて広範な領域に跨る」と指摘する。同氏に、税と保険の現状や問題点を中心に伺った。(取材・小柳)
■保険税務の通達に対する専門家の意識
「租税法律主義の下で税理士などの租税専門家には、税務通達をどのように実務に生かすべきかが問われています」
通達は決して法律と同じものではなく、単に行政官庁における上意下達の命令であることを常に念頭に置く必要があると指摘する。
「そうした理解が保険税務の大前提です。なぜなら保険税務の取り扱いの多くは、通達にルールが示されているからです」
通達が法律ではないことを忘れると、〈通達にこう書いてあるから間違いない〉という単純思考に陥り、法律解釈が二の次になってしまうと示唆する。
「しばしば税理士が自らのことを〈実務家であるから〉と通達に自分が従うのはしょうがないという意味でそのことを免罪符にしているかのような風景に出くわします」
通達を法律かの如くに理解することが、実務家であれば許されると免罪符にする。
「そう理解せず租税法律主義の下で、通達には法源性がないことを頭では理解していながら、いざ実務的処理を行うとき、通達に従順であるという姿をそこに見ることがあります」
これは極めて危険な姿勢と警告する。
「ひと口に言えば、通達がセーフティハーバー(安全地帯)になる保証はないからです。実務家であれば、そこにリスクがあることを十分に承知した上で実務に当たりアドバイスを行うべきです」
近著『クローズアップ保険税務』は、これまで通達に記載されていることや、他の書籍で問題ないとされていた内容について法律家の観点から検討を加え、リスク可能性事例を例示した。
「通達を批判する内容ではありません。そういう編集・監修は一切行っていません。通達の持つ極めて重要な行政上の機能を十分に認識し、しかしそれは法律ではないがゆえにいつ改訂されても文句は言えないことを念頭に置く必要があるという問題意識で執筆しました」
これらは、国税庁時代に通達発遣の仕事に携わった経験が基礎になっている。
「例えば保険の税務上の取り扱いをアドバイスする税理士などの租税専門家は、通達に記載されたルールが国会で国民が承認した法的ルールではないということを理解した実務家であるべきです」
それが真の法律家としての税理士の姿と考える。
「法律家としての税理士を自認しているはずの人たちが、何の疑問も持たずに通達をあたかも金科玉条の如く取り扱っている場面に出合うと、そこに言う法律家が何を意味しているのか不安を覚えます」
■逆ハーフタックスプラン
「通達に従って商品化するのは分かりますが、通達さえもない保険の取り扱いに関しては大きな不安があります」
逆ハーフタックスプランを分りやすい事例として挙げる。
「福利厚生のための養老保険で、満期保険金受取人を従業員等として死亡保険金受取人を法人とするプランです。保険金受取人が法人、死亡保険金受取人が従業員等の遺族という、いわゆるハーフタックスプランの逆となるタイプですが、これに該当する通達はありません」
会社は、①役員を被保険者として保険に入り保険料を支払い、②福利厚生費として2分の1が損金扱い、③積立部分については役員に対する給与として2分の1が損金扱いと考えると、結果的に④支払い保険料の全額が損金扱いになる。
「このような取り扱いが許容されるか否かについての直接的な通達はありません」
この逆ハーフタックスプランを巡っては、最高裁が平成24年1月に判決を下している。
「保険の満期返戻金を役員が受け取ったとき、個人所得税法の金額の計算が争点となりました」
会社が損金にした保険料を個人所得税の金額の計算上控除することができるか否かが争われた。
「課税庁は、いったん法人で損金にして置きながら、満期返戻金を受け取った個人の所得税の金額の計算をする際にまた保険料を控除することになると、いわゆる二重控除となることから個人所得税の金額の計算においてその保険料を控除することはできないと主張しました」
最高裁は結局、課税庁側の主張を認めた。
「所得税の条文には、〈支払った金額を控除する〉とだけあり、誰が支払ったかについては明確にしていないという納税者側の主張は通りませんでした」
平成24年1月の、この最高裁判決をもって〈法人税の金額の計算上、損金を差し引くことを最高裁判決は認めた〉と解釈できるという意見もある。
「全ての判決は、個々の訴訟物を対象としており、この場合は所得税法上の計算が訴訟物だったのです。当事者主義(弁論主義)という裁判のルールの下、当然ながら法人税法上の処理の適否は争点ではありません。最高裁が法人税法上の取り扱いを認めたと理解するのは全くの誤解と云うべきです」
節税効果が得られる様々な保険契約がある中で大事なのは、〈このケースは税務当局から否認されるかもしれない〉という情報に基づき選択すること。
「税理士などの租税専門家は、節税メリットだけではなく、否認されるリスクを正確かつ明確にアドバイスする責任があります」
節税商品を巡っては、様々な租税専門家責任が提起されている。
「アメリカでは、タックス・シェルター・マルプラクティスと言って、節税商品過誤訴訟が大きな問題となっています」
同氏は、タックス・シェルター・マルプラクティスの法的研究で博士号を取得し、これら事情に精通している。
「法人税法や所得税法には、同族会社等の行為計算の否認規定があります。同族会社等を絡めた不当な節税については、仮にそれが私法上有効な契約であるとしても、国税当局が公権力を発動して否認することができるという規定です」
租税専門家は、こうした規定があることを承知した上で、節税上のアドバイスを行うべきと示唆する。
「社会通念上おかしくない保険商品が標準です。保険を節税に役立てること自体は問題ありませんが、本来の保険機能という観点から見て逸脱していると思われる税務処理は一度疑って掛かる慎重さが肝要です」
税理士や保険会社は、法律的な検証を怠るべきではないという立場に拘る。