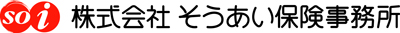『小金井通信』Dシリーズ 2025年10月 ◆「週刊保険情報」2017年6月
【アーカイブ】「週刊保険情報」2017年6月
生保募集人出身の吉田由紀子(仮称)代理店主に聞く
都内信金、都市銀行勤務を経て、大手生保営業職員に応募し11年在籍したのち、独立し保険代理店を開業。金融機関代理店の動向や保険窓販解禁を見据え、一社専属募集に限界を感じての転身だった。金融業界のキャリアは35年以上、保険営業のキャリア25年に及ぶ女性代理店主をJR両国駅に近い事務所に訪ねた。(取材・小柳)
●乗合代理店の将来
「生保の営業職員が保険代理店として独立するには、高い障壁がありました」
そんな時代背景の中で事務所は4人でスタートした。
「損保の代申会社は東京海上日動です。当時の東京海上に協力を求めました」
その後、損保ジャパン日本興亜、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保に乗り合う。昨年の改正保険業法施行前に委託型募集人1人が独立した。
「改正保険業法施行を機に、第一生命、東京海上あんしん生命、アフラック3社の推奨販売に移行しました」
生保は、日本・明治安田・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命も取り扱う。
「アフラックは医療保険を中心に取り扱います。定期・終身保険から無選択型まで500万円までの死亡保障にお応えできます」
顧客ニードに柔軟に対応でき優れている。
「募集人を採用するには、自らが乗合商品の取り扱い要領をマスターすることが肝心です。保険会社の営業社員の皆さんと連携を図り、募集体制を整えています」
事務所の営業体制を整えたのち、人材を確保する方針。
●商品選択の基準
「保険募集は案外、1社専属で商品提案するほうがすっきりすると思います」
あれこれ考えず、簡潔な提案ができると考える一方、それではプロのコンサルタントと言えるだろうかと自問自答する。
「法人契約先によっては、資金繰りが困難に陥り契約者貸し付けを希望されるケースがあります。保障を提案する際には、法人先の経営内容等を慎重に吟味することです」
契約者貸付制度の概要を説明し、事業の先々について確認することが肝心。
「保険会社毎に各商品のメリット・デメリットを分析し、取り扱いの軸になる主力商品をあらかじめ決めておきます。〈一時払い商品は××生命が一押し〉、〈契約年齢では○○生命は80歳まで、××生命は85歳まで〉といった具合に商品特性をつぶさに把握します」
契約先の実態を把握すると、提案商品は自ずと決まる。
●どの保険が一番優れているか!
「お客さまとお話しする中で困ることがあります。それは〈どれがよい商品?〉と単刀直入にご質問されたときです」
〈保険に優劣やよしあしはありません。お客さまにとって最適な保障がベストです〉と答える。法人・個人を問わず、どこに保障のポイントを置くかがコンサルティングの胆。
「最適な保障を提案するには、とにかくお客さまの話しの隅々まで、家族関係やそのとき抱えている悩みなど細部まで洩らさないことです」
保障か、税効果か、その両方かを聞き洩らさない。個人の胸襟まで踏み込む保険募集は細心の注意が肝心。
●契約保全
「お客さまが保険に加入する目的は、万が一の保障を得るためです。万が一のとき、その手続きは万全でなければなりません」
保険募集人は、契約保全が何より大切。
「お客さまが当社に契約を委ねてくださるのは、信頼関係にほかなりません」
保険募集は、通販、インターネット販売、銀行窓販、来店型保険ショップと多様化の一途を辿ってきた。
「保険は、加入することや見直すことが目的ではありません。万が一のときの保障とスムーズな支払いが肝心です」
保険の趣旨を曲げた広告宣伝が大手を振っている風潮に警鐘を鳴らす。
●生・損保併売の多様化
「私たちは生保が出発点ですから、生保のお客さまに対する損保商品の併売からスタートしました」
現状は、損保顧客に対する生保商品の併売も多く、半々といったところ。
「損保の契約先からお客さまをご紹介していただき損保や生保をご提案するケースもあれば、生保の契約先からお客さまをご紹介していただき生保や損保をご提案するケースもあります」
取り扱いは多様化し、さまざまな併売パターンがある。
「生保分野或いは損保分野をご提案するにとどまらず、お客さまの暮らしや事業活動をトータルにカバーする中で信頼を醸成するよう創意工夫を心掛けています」
10数年前、地域密着型営業を標榜し東京・墨田区に事務所を構えた。
「当初は、損保系代理店のように建設業とか、食品関係とか、取扱先の絞り込みを模索しました」
紹介先は地元とは限らず、業種を特定する必要もなかった。
「私は大手生命出身ですが、このとき受けた教育研修が今日の礎になっています」
保険会社は、営業職員が顧客対応力を発揮できるよう資料を整える。それに基づき、日々の営業活動に励んだ。
●改正保険業法施行後の対応
「昨年5月に施行した新しい募集ルールにより意向把握義務や情報提供義務が導入されました。募集人は、お客さまのご意向を把握し、そのご意向に沿った商品提案や説明を行い、お客さまのご意向と契約内容が合致しているかを確認する一連の運用が求められています」
こうした新たなプロセスを踏襲することはもちろん不可欠。
「お客さまのご納得が得られない未成熟な募集人の取り扱いがあったことが、改正保険業法施行の事態を招きました」
商品売りに陥ることなく、顧客ニードの原点に立ち返り、顧客の声に耳を傾けるよう徹底する。
●生保募集の特殊性
「生保販売では、人生の積み重ねや経験が幅を利かせます。大病の経験があるとか、遺産相続でご苦労されたとか、募集人の人生の蓄積が若年層や未経験者の糧として役立ちます」
60歳の坂を越えた募集人にも、もちろん人生設計はある。
「仕事量は、50代の半分くらい週3日程度にセーブし、豊かな暮らしや人生を謳歌したいという希望や願いもあります」
昨年施行した募集人や保険代理店に対する一連の規制強化は、募集人の適度な労働環境を維持することを許さない。
「経営的な観点で言えば、若年層と同一の業務量をこなさなければ社会保険料負担等で雇用することはかないません」
政府は、働き方改革や多様性など広範で多様な社会のあり方を提唱する以上、保険募集人にも多様な働き方を認めるべきと論陣を張る。
「高齢化社会が到来し、団塊世代が65歳以上に達し、居酒屋やコンビニなど多くの業種で来店客と同世代の高齢パートタイマーの求人が増える傾向です」
長年にわたり生・損保業界で培ってきた知見を活用する創意工夫があって然るべきと考える。
〈取材メモ〉埼玉県西部の40代半ばのある代理店主は、母親から代理店を引き継いだ。母親は、大手生保から東京海上の研修生になり今日を築いた。40代半ばの店主は、友人と2人で「××通信」取扱店として独立したものの、事業に失敗した。
そんなとき、母親から後継者として事業を託された。収入保険料は9000万円ほど。手数料収入は、損保が1560万円、生保が120万円、合計すると1800万円ほどになる。事務所の体制は、店主と両親、事務員の4名体制。営業の9割弱は自らが担い、70代の両親は1割強。
新規顧客の獲得は、商工会議所やPTAなど地域活動で知り合った人たちや既存客からの紹介。本人曰く、「あまり積極的とは言えません。熱意は以前の8割くらいです。脱保険代理店業を掲げ、他業種へ経営の舵を切っています」。両親の経営基盤を引き継いだ店主には、保険の水は合わなかったようだ。またFP資格を取得して以降、生保販売に対する意欲が減速したと振り返る。「手間の割に対価が少ない」と考えるようになった。生保募集は、個人事業主等からの依頼に基づき取り扱う。