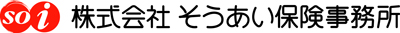『小金井通信』 2025年8月
●関東・東海財務局、8月6日付で国内最大訪問型乗合代理店『FPパートナー』及び自動車販売・修理ディーラー損保代理店『ネクステージ』に行政処分
(取材・小柳博之)
8月6日付で、関東財務局が『FPパートナー』(東京都文京区)に対して、及び東海財務局が『ネクステージ』(愛知県名古屋市)に対して、行政処分を発出したことを受け、金融庁監督局保険課の下井善博保険課長及び佐藤寿昭生命保険モニタリング長、矢野雅隆損害保険モニタリング長は6日17時30分から「保険代理店に対する行政処分」について記者ブリーフィングを行った。
関東財務局は、保険業法第306条「業務改善命令」(特定保険募集人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるとき、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる)に基づき、業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、社外監査役等に対し、現状における取締役会の機能発揮状況に係る課題認識、並びに業務の改善計画の進捗及び改善状況に係る実効性評価等について、意見を表明させること及び業務の改善計画及び意見表明内容を今秋10月6日までに提出し、業務の改善計画の内容について直ちに実行すること、又これらに係る改善計画の6か月毎における進捗及び改善状況並びに意見表明内容を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を2026年4月末)、改善計画及び報告した改善計画の進捗、改善状況についてその都度、同社ホームページで概要を公表するよう求めた。
今回の処分理由について、関東財務局では「FPパートナーは、2024年11月末時点で全国に174拠点、2518人の保険募集人を有する訪問型保険代理店業界最大手の乗合代理店。複数の保険会社の保険商品のうち、予め選定した推奨商品の中から顧客の意向を踏まえて特定の商品を説明する募集方法を採用している。こうしたビジネスモデルの場合には、意向把握・確認義務を適切に履行することが極めて重要であるが、同社では保険募集人がこうした義務を果たしているか否かが確認できる態勢が整備されておらず、その適切性を担保できない状況にある」と判断した。
また、同社は、保険会社からの便宜供与の実績に重点を置き推奨商品の選定を行っており、この点について社外監査役から、「定性評価だけでは恣意的と捉えられかねない」旨の指摘を受けていたにもかかわらず、1年超に渡り具体的な対応を怠っていた。
今回検査を行うと、顧客の意向に合致しない商品を勧められたといった苦情や、顧客意向と異なる商品(収入保障のみを希望する顧客に変額保険を提案するなど)を推奨している事例が認められた。また、医療保障を希望する顧客に対し、同保障に対応した推奨商品のうち特定の保険商品のみを提案する事例が多数存在し、合理的な理由なく特定の保険会社を偏重・推奨していることが強く疑われる実態が認められた。
これらに照らし合わせると、同社では顧客の適切な商品選択の機会が阻害されている蓋然性が高く、訪問型保険代理店業界最大手であり、かつ乗合代理店の中にあって突出して毎年多くの新契約を獲得していることなどを踏まえると、乗合代理店ひいては生命保険業界における比較推奨販売に対する信頼性を著しく毀損すると断定した。
これを是正するためには、経営陣による適切な関与の下、ビジネスモデルの特性に応じた保険募集管理態勢の確立を含む実効的な態勢整備に取り組む必要があるが、経営陣はこうした推奨販売におけるリスクを認識せず、保険会社からの便宜供与の実績を重視した保険募集管理態勢を構築しており、今後同社による保険募集の公正を確保し、保険契約者等の保護を図るには金融当局の関与が必要と判断した。
同社では、大半の保険募集人に対し、成果連動型の報酬体系を適用し、保険会社から受領した代理店手数料に一定の支給率等を乗じて算定した金額を報酬として支払っており、保険募集人が本人やその家族(同一生計)の契約を取り扱った場合、当該契約に対して報酬を支払うことが、保険料の割戻し等に該当しないかどうかの検討が全く行われていなかった。
このため、今回の検査では、今年1月時点で有効な本人契約3775件のうち、3765契約について保険募集人に対し同社が受領した代理店手数料の一部が支払われ、
保険業法第300条第1項第5号「特別な利益の提供を約束したり提供する行為」(保険募集人が契約者又は被保険者に対して保険料の割り引き、割り戻し、その他特別利益の提供を約束すること、又は提供すること。具体的には、保険に入ってくれたら特別に一回目の保険料は私が払いますから等の保険契約者に対して特別利益を提供する行為などに、違反している事実が認められた。
東海財務局は今回、「業務改善命令」に基き①経営責任の所在の明確化、②コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成、③適切な保険募集管理態勢の確立、④適切な苦情管理態勢及び顧客情報管理態勢の確立、⑤これらを着実に実行し定着を図るためのガバナンス態勢の抜本的な強化を求めた。併せて、業務改善計画を今秋9月8日までに提出し直ちに実行すること及び同改善計画を3か月毎の進捗及び改善状況を翌月 15 日までに報告すること(初回報告基準日を2025年 12 月末)を求めた。
今回の処分理由について、東海財務局では「ネクステージは、同業他社における保険金不正請求問題の発覚を受け、2023年8月、顧客、取引先及び株主等の関係者への説明のため自主調査を行い、不正請求事案が確認されなかった旨を公表。その後、同年9月初旬以降、同社における不適切募集や不正請求に関する報道が行われてきたことを受け、従業員による自動車保険契約の捏造など一部事実であることを認め、その旨を公表。さらに、同月には主要取引銀行の要請を受け、外部弁護士による内部調査委員会を設置し、同社事業の適法性、健全性を再検証した。
その結果、同委員会は同年 10 月、「組織的な関与を含む不正請求事案等は確認されなかった」旨を報告書として取りまとめ、損保会社による調査に適切に対応するとともに、板金修理の見積作成、損害保険会社との協定業務を現場から本部の専門性の高い部署に移行するなど、不正請求が発生しにくい体制の構築に取り組んできたとしていた。
しかし、今回立ち入り検査を行うと、①経営陣は「問題がない」との結論ありきであり、調査期間や調査の実施主体など、自主調査の適切性等に関する事項について、取締役会等で全く検討・議論していないまま、整備業務を所管する整備本部に調査を実施させている。②これを受けて、整備本部は同本部に所属する従業員に調査を行わせているが、統一的な確認の基準もない中で、これらの従業員は各々の主観に基づいて関係資料を確認しているため、調査の客観性が担保されておらず、問題がないとの判断を裏付ける証拠も残していないなど、調査方法が不十分だった。③整備本部は、調査対象期間や調査対象範囲についての適切な検討を行わないまま、調査開始時点から直近3か月の案件を対象として調査を開始したものの、同社の板金修理売上の9割以上を占める外注先工場での修理案件のうち、関係資料が揃っていないなど不正請求の蓋然性がより高いと考えられる案件を調査対象外とする等、調査対象が限定的な範囲にとどまっていた。