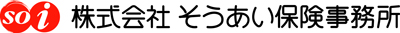『小金井通信』 2025年5月 ◆「月刊ライト」2009年9月号
昨春、サンフランシスコ州立大学を定年退職した、後藤幸弘前教授に一時帰国中に再会すると「トランプ政権の影響で米国籍を取得した。これでアメリカ人になった。日本に帰国するときは、妻の日本国籍に頼らざるを得ない」と厳しい現実に直面していることを明かした。
ちなみに、米国の大学には定年はなく、生涯働き続けることも可能。米国の年金制度は、自分で積み立てた持ち分を60歳から受給する仕組み。ただ、70歳までは半額しか受給できない。(取材・小柳博之)
【アーカイブ】「月刊ライト」2009年9月号
「ショートインタビュー」
サンフランシスコ州立大学 後藤幸弘演劇学部教授に聞く
〈プロフィール〉ごとう・ゆきひろ:サンフランシスコ州立大学演劇学部教授/学部長/博士/1954年福岡県まれ/1975年渡米
後藤教授は日本人の素晴らしさ、例えば心構えや礼儀正しさ、自分に対する厳しさを学生に教える。それは、米国人には決して真似のできない、日本人としての本分と考えるからにほかならない。とはいえ、「どの先生のよいところを学ぶかは学生自身が決めることです。何か一つだけが正しいということはありません」と米国流の原理原則も忘れない。正座を30分やっても、学生たちは痛い、痛いと言いながらもついてくる。
「演劇は、舞台に立ってから始めるのではありません。その前からすでに始まっています。実はオーディションも、会場に行くときから始まっています。ところが、これに気付く学生はほとんどいません」。
夏期休暇で帰国中のサンフランシスコ州立大学演劇学部教授(学部長)である後藤幸弘博士にリーマンショック後の米国社会や、『9.11』以降の米国社会の変貌について伺った。
(取材・構成=編集部・小柳)
●後藤先生は渡米し、30年以上米国で暮らしています。この間に、建国200年記念も経験していますが、オバマ大統領が誕生した現在と渡米当時とでは何が変わったでしょうか。
「やっぱり、『9.11』です。米国社会は、あの日から本当に変わったと思います。日本語でいえば、震撼でしょうか。私自身、あの日のことはよく覚えています。米国でも昔の人は、ケネディー大統領の暗殺の記憶がよみがえるといいますが、米国人にとってはそれ以来のメモリアルデーではなかったかと思います。
それは、米国内での初めての戦争であり、しかも子どもを巻き添えにした戦争だったため、米国社会は震撼しました。
あの朝、私は学校の駐車場からオフィスに向かっていました。すると、学生たちが下校しています。涙を流している女子学生もいました。
〈どうしたのか〉と一人の女子学生に尋ねると、飛行機がぶつかったといいます。事故でも起きたのかと思い、さらに聞くと〈ノー、アタックされた〉といいます。
私のオフィスにはケーブルテレビがありましたから、急いでテレビをつけました。すると、2機目の飛行機がWTCに突っ込んでいく映像が映っていました。何度も何度も繰り返していました。
そして、ニューヨークからサンフランシスコに向かって飛行機が来るというのでずいぶん緊張しました。
それで、何が変わったかと言えば、日本的に言えば、〝内と外の論理〟でしょうか。米国は移民の国ですから、基本的に誰でもウエルカムです。一所懸命でさえあれば、誰でも受け入れてくれるキャパシティがあります。
しかし、この戦争を境として、米国人と外国人の間の一線が明確になりました。外国人は信用しないという敵と味方の境界線です。例えば、日本では中近東の人が疑われると思うかもしれませんが、アジア人であれ何であれ、のほほんとはしていられない空気ができました。それをひしひしと感じます。
サンフランシスコでは、実は、白人はマイノリティなのですが……そして、私のように市民権を持っていないと著しく不利です。こんなことがありました。
前回、日本から帰国したときです。直行便がなかったためLA経由でサンフランシスコに戻りました。私のグリーンカードは、現在使われていない古いタイプだったため、移民局で〈なぜ新しいタイプに切り替えていないのか〉と問い詰められました。しかも〈切り替えなさいよ〉といったニュアンスではなく、明らかにおかしいという眼差しです。指紋と目の写真を取られ、厳しい質問が飛んできました。
実は、米国で暮らす外国人は皆、市民権を待望しています。5年経つと取得できます。現在のグリーンカードは10年ごとに更新しなければならず、古いタイプのグリーンカードが存在すること自体が稀有です。私のグリーンカードは、それ以前であるため更新しなくてもよいわけです。これで、もし英語が話せなければ、完全に犯人扱いだったと思います」
●そういう米国社会に対して、日本育ちの米国人としては、どういう感じを抱くのでしょうか。
「もちろん不健全だと思います。日本でいう疑心暗鬼はよくありません。そもそもまず疑うことは米国の精神ではありません。
30数年前の米国人は、疑う前にまず好奇心の眼差しを向けました」
●『9.11』以降、猜疑心が幅を利かせる米国社会へと変貌したわけですが、後藤先生が米国に留学した理由は何だったのでしょうか。
「どうして渡米したかと言えば、米国に憧れたからではありません。日本にいたくなかったからです。そういう意味では、ベトナムでも、タイでも、ドイツでもよかったわけです。
日本で1970年代に青春だった世代は、私は逃避行の世代だと思います。学生運動の挫折等に象徴されるように、社会にもやもやしたものが満ちていました。自分の居場所を求め、どこか遠くへギター一本でさすらいの旅に出たわけです。
大学では、英文専攻でしたから、英語を勉強し帰国後は英語の先生になるという大義が米国にはありました。2年間という約束で出発しました。
ウィスコンシン大学、カンサス大学、ミネソタ大学を経て、ハワイ大学に辿り着きました。13年に及ぶ学生生活です。
私は、M.F.A.(Master of Fine Arts)とB.F.A. (Bachelor of Fine Arts)を取得していたため、ハワイ大学では講師として採用してくれました。またグリーンカードも取得できました。ハワイ大学の博士課程に席を置き、講師として働き、講師の収入で生活することができました。さらに米国政府から4年間奨学金をもらいました。
卒業後、ニューヨーク大学に2年間在職したのち、現在のサンフランシスコ州立大学が教授として迎えてくれました。サンフランシスコは、米国で最初に土を踏んだ場所ですから、二つ返事でした」
●日本では昨秋、米国発のリーマン(AIG)ショックによって大打撃を受けましたが、米国市民はこれをどのように受け止めているのでしょうか。
「全てはサブプライムローンの焦げ付きに端を発しています。これは、市民生活に大きな影響をもたらしました。
地価が変わり、預貯金金利や貸付金利が変わり、物価も変わりました。これは、やはりローンを払えない人にまでお金を貸した銀行が悪かったと思います。日本のバブル期と同じで、とにかく何でも買い付け、何でも消費するありさまでした。
銀行は、絶対に返済できないことを承知でローンを組みました。最初の5年は低利です。その後ボーンと利息が膨らむタイプです。そこで皆破綻したわけです。
米国人は、結構いい加減で、何しろ預貯金はしません。プラスティク・カードだけで生活しています。米国政府は、国民があまりにも預貯金をしないため、預貯金口座の一定額(2500万円)を保証するほどです。
要するに、移民はアメリカン・ドリームと勘違いしました。アメリカン・ドリームとは、家を持つことにほかなりません。
私の住んでいる大学に近い一帯の一軒家の相場は、2ベッドルーム、1リビングルーム、ガレージ付きで8000万円です。サイズは違いますが、千葉の実家の近くでは2000万円ほどです。サンフランシスコの地価は今も下がっていません」
●リーマンショックを経て、米国人は何かの教訓を得たでしょうか、あるいは変わったでしょうか。
「米国社会は、他国民性だから難しいと思います。日本にも韓国人や中国人、アジア人もいるでしょうが、だいたい同じような考え方です。
しかし、米国人は、一つの考え方で推し量ったり、動いたりできない多様性がありますから、たぶん今回から何かの教訓を得ることは難しいでしょう」
●今回は、破綻した保険会社・証券会社と救済された保険会社・証券会社で明暗を分けたわけですが、米国社会ではこれをどのようにみているのでしょうか。
「米国人も、それについては不公平だと思っています。ただし、AIGが潰れるともっと悲惨な事態になっていたと感じていたかもしれません。
公務員は、ベネフィットは少ないですが、こういうときは強いわけです。ところが、カリフォルニア州は今、大赤字ですからそうともいっていられない状態です」