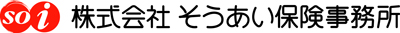『小金井通信』 2025年10月 ◆「月刊ライト」2009年3月号
【アーカイブ】「月刊ライト」2009年3月号「ワイド・インタビュー」 (取材・小柳博之)
インターリスク総研
本田茂樹 研究開発部主席コンサルタント
/篠原雅道主任研究員に聞く
もうそこまで来ている!
新型インフルエンザの最前線
このところ、中国から伝えられる鳥インフルエンザ(「トリ・ヒト」感染)による死亡報道を耳にすると、「新型インフルエンザもそう遠くない?」との感を強くするが、果たして。
新型インフルエンザは、鳥インフルエンザ『H5N1型ウイルス』が変異し、ヒトからヒトへ感染する現象である。2008年11月号本誌で伝えたように、わが国における健康被害は厚生労働省の推計によると、「発症25%、入院~210万人、死亡~64万人(人口1億2800万人)」の猛威である。海外の研究機関等では、これを上回る被害推定データもある。
そして、いったんパンデミックに陥ると、社会全体が底なし沼に嵌り込んだように身動きが取れなくなり、派遣切りや空転国会など経済や政治の歪みも絵空事に過ぎない、壮絶な事態へ発展することは間違いない。
新型インフルエンザの最前線を注視する三井住友海上グループのインターリスク総研(インターリスク)研究開発部に本田茂樹主席コンサルタント(昭和52年4月現三井住友海上入社。昭和28年8月生まれ、55歳。慶応義塾大学卒業)と篠原雅道主任研究員(平成4年4月現三井住友海上入社。昭和42年2月生まれ、42歳。九州大学卒業)を訪ねた。(取材=編集部・小柳)
――わが国では昨春(2008年)、東北の十和田湖で白鳥が鳥インフルエンザに感染した事例が見つかりました。ちょうどこの頃、改正感染症法が施行されました。
新型インフルエンザ(鳥インフルエンザ)は感染症法で位置付けられていなかったため、2008年4月に改正し5月から施行しました。新型インフルエンザをⅠ類の感染症と同格にすることで、発症時の水際対策を行いやすくするのがこの狙いです。
政府の行動計画やガイドラインでは、昨年7月30日に第8回新型インフルエンザ専門家会議を開催し、翌月13日に公表した『事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン』の改定案を取りまとめました。
この改定版で初めて、新型インフルエンザが発症するとどうなるかというシナリオが示されました。事業者の立場では、「こんな事態に陥るのであれば、何らかの措置を講じなければ」とか、「こんなに欠勤率が高いなら、この対策が必要だ」といった議論になります。ガイドラインのパブリックコメントは9月末に締め切り、11月28日の第10回新型インフルエンザ専門家会議で了承されました。
一方、『新型インフルエンザ対策行動計画』は、11月28日の専門家会議で了承し、12月末までパブリックコメントを募集しました。新型インフルエンザに関する行動計画及び事業者以外のガイドラインの細目は、今年度中にも公表される方向です。これにより国から発出される一連の施策は、格段に整備されます。
――人類は過去にも、コレラやペスト、スペイン風邪(インフルエンザ)といった具合に、多くのパンデミックを経験しました。現在の医療水準と比較するとほとんど絶望的な事態です。それでも、これを克服してきました。そういう意味では、今回は早めに手を打つことが最善です。また、海外の日系企業でも、たくさんの日本人が働いており、企業も、そして政府も、こうした皆さんを顧みる必要があるはずです。
実は、2008年11月にインドネシアへ出張しました。鳥インフルエンザの現地事情を調査することが目的です。インドネシアは、世界で最も多く鳥インフルエンザが発生している地域です。
調査で得た感触では、現地の日本人は危機感をもってこの問題に対処していました。私は、日本大使館や日系の病院、現地の感染症指定病院、そのほか日系企業やジャパンクラブ、インドネシア保健省も訪ねました。調査の一方、日系企業を対象としたセミナーも開催しました。参加者が当初予測を上回ったため、急遽会場を変更するほどでした。
今回の調査では、日本本社とインドネシア現地法人の意識の違いを感じました。インドネシアの日系企業では、鳥インフルエンザが頻発する中で様々な対策を講じる必要性を感じています。したがって、対策を進めるに当たっては、日本本社と連携を密にする必要があります。しかし、日本本社の方針が固まっていなかったり、或いは動きがスローだったり、インドネシアの事情がよく分かっていなかったりと様々な問題点が明らかになりました。
ひと口に言えば、インドネシアでしか分かりえない事情がたくさんある以上、現地で様々なアイデアを出し、それを日本本社にぶつけ、また本社も現地に入り実際に肌で感じながら対策を練るべきと考えるようになりました。
たとえば、新型インフルエンザ発生の際、日本人が帰国するめどは付いていません。日本政府の水際対策で想定される海外からの帰国者を受け入れる限度は1日に1500人程度です。インドネシア以外の中国、ベトナムから帰国したい人たちもいます。インドネシア在住の日本人は1万人以上ですから、発生後の帰国は非常に困難です。
一方、医療レベルも問題です。日本の医療レベルは恵まれています。実は、感染症指定病院にも足を運びました、スラム街の真っ只中にありました。私はクルマで行きました。ところが、道幅は狭く、地理に不案内な日本人が足を運ぶことはとうてい困難だと感じました。医療設備も、決して高いレベルとは言えません。
――ローカルスタッフと日本人の意識の違いといった面で支障を来たすことはないのでしょうか。
ローカルスタッフであれ、日本人であれ、感染するリスクは同じです。日本人の場合、本社から指示など一定の情報を有し、新型インフルエンザに対する理解があります。ところが、大多数のローカルスタッフは厳しい環境に晒されています。
この要因はいくつかありますが、政府からのリリース含め情報が少ないためです。またインドネシアで法定伝染病と言えば、デング熱です。デング熱の脅威のほうが一般的には勝ります。インドネシア政府は、欧米やWHOと必ずしも足並みを揃えておらず、こうした難しさもあります。
たとえば、インドネシア政府が出国禁止令を出すような事態を想定して、航空券のオープンチケットを用意しておくことや、いざというときには隣国オーストラリアに一時避難するなど、多様な対策を講じておく必要があると思います。いずれにせよ、感染予防策と事業継続両面に関する対策は、現地任せではなく、日本本社がしっかりサポートすることが大切です。
――新型インフルエンザの潜伏期間は、2~4日程度と言われますが、この期間に感染者が飛行機に乗ったため機内に新型インフルエンザをまき散らす事態も想定できます。そうなると、退避自体も難しい選択ですね。
おっしゃるようなリスクはあります。機内で発症し咳など飛沫によってウイルスをまき散らすことは十分に考えられます。マスクの携帯や着用は不可欠です。WHOが『フェーズ4』を宣言した段階で、『フェーズ4』は小集団のヒト・ヒト感染のことでまだ拡散が限定されている状態ですが、日本ではまだ発生が確認されておらず、発生国から感染のおそれのある人が搭乗する可能性があれば、直行便を止めることが想定されます。
そうなると、その国にいる日本人は帰国できなくなります。こうした場合、政府専用機や自衛隊機で対処するわけですが、飛行機のキャパシティー(自衛隊機約は90名、政府専用機約350名)からいっても帰国は不可能です。現状では、在外公館が現地の医療機関を紹介するといった手立てしか残っていません。
翻って言えば、『フェーズ4』の前に帰国する算段をしておかなければ帰国できません。日本政府は、海外危険情報を出す方針ですが、これが十分に機能するかは予測不可能です。
実は、帰国することが本当に最良の方策かという問題もあります。暴動やテロなど、帰国しなければただちに身に危険が迫っている場合、第三国を経由してでもただちに出国するべきです。しかし、リスクを取って帰国したにもかかわらず、帰国した日本も既に新型インフルエンザが蔓延し、しかも帰国した駐在員用の社宅の空きも物資の備蓄もないという事態だって考えられます。
パンデミックが半年、1年と続くことを考えれば、これは大変なことです。インターリスクのアンケート調査では、帰国させないという企業もありました。その代わり、現地でしっかりと感染予防、備蓄、事業継続といった新型インフルエンザ対策を行うという考え方です。
数年前、『SARS』が流行したとき、国外退避した日本人に対して「自分たちだけ退避するのはおかしい」といった論調がありました。これがトラウマになっている日系企業もあるようです。ローカルの人間と日本人がしっかりコミュニケーションを取り、対応を事前に定めることが必要です。
もちろん、帰国することが間違っているわけではありません。しかし、帰国させるからにはそれだけの算段が必要です。アンケートでは、未定という回答が50%弱、また残留と国外退避はそれぞれ10%弱でした。経理など経営的な観点で日本人が担っている部分もあり、帰国できない事情もあるようです。
インドネシアのある化学メーカーでは、新型インフルエンザが発生した場合、ただちにオペレーションをストップさせて家庭で十分に待機してもらう方針を打ち出しています。日本本社の承認も得ています。会社によって、また経営判断によって様々な選択肢があるようです。
とはいえ、現地法人トップと経理責任者だけは、やはり残らざるを得ないというのが大方でしょうか。また、『SARS』の教訓から「ローカルスタッフには丁寧な説明を」というのが一致した考え方です。
ひと口に帰国と言っても、パンデミックの場合、1年超のスパンの中で何回かの波を繰り返すことが想定されます。ですから第1波が収まり、すぐに現地に戻ることには疑問を感じます。いざ戻ると、実は第2波が押し寄せていることも想定できます。国外退避する場合、あらかじめその後の行動計画についても考慮しておくことが肝心です。
――厚生労働省は、鳥インフルエンザに関するサイトを立ち上げ、WHOが公表する鳥インフルエンザに関する発生国と人の発症事例を明らかにしています。
今年2月2日時点では、インドネシアは2003年からの累計で141人が発症し、このうち115人が死亡しています。インドネシアの消息筋から得た話では、州単位で調査を行うと新たな鳥インフルエンザ感染者が見つかると言います。つまり、未調査の地域がたくさんあるということです。
――発症例、死亡者数ともインドネシアとベトナムが圧倒的に多いわけですが、これはどうしてでしょうか。
まず、鶏、豚、牛等の家畜を一緒に飼育すること、また人がその周りで暮らす風土があることではないでしょうか。日本では、鶏は鶏だけで飼育するのが一般的です。さらに屋根や囲いのある飼育場がほとんどです。野鳥等が入り込む余地はほとんどありません。
インドネシアでは、野外で鶏も豚も放し飼いです。池ではアヒルが泳いでいます。鳥インフルエンザは、そもそもアヒルなど野生の水禽類の腸管で増殖し鳥間で糞を媒介に感染しますが、それが鶏や鶉、七面鳥に感染し、さらに豚を介するとウイルスは変異します。雑多な動物が混在する場所は、ウイルスが変異しやすい場所です。
――イスラム教の国ですから、豚を食す習慣がないことが鶏を飼うことと関係しているのでしょうか。周辺国はどうなのでしょうか。
たとえば、東京でどのくらいの人が鶏を飼育しているかと言えば、ほとんど飼っていません。しかし、インドネシアやタイでは、鶏を飼うことはごく普通です。中国やインドネシアの市場では、生きている鶏の売買や、そこで捌いた鶏肉の販売を行っています。鶏は貴重な蛋白源であり、また財産だからです。
発展途上国では、少なからず貧富の格差があります。鶏は食文化と密接に関係しており、生活基盤そのものと言っても過言ではありません。ですから一概に非難することもできません。
一方、インドネシア政府は、鳥インフルエンザに関する情報をタイムリーに出しているわけではありません。数か月に一度、公表する程度です。日本や欧米とはスタンスが少し異なりますから、インドネシアでは鳥インフルエンザの脅威はなかなか浸透しないわけです。
――三井住友海上のアジアの位置付けと、アジアにおけるインドネシアにいる日本人の状況はどの程度でしょうか。
三井住友海上のシェアでは、インドネシアはアジアNo.1です。インドネシアには相当数の日系企業が進出しています。1万人以上の日本人が暮らしていますから、工場の数もタイと並びアジアでは有数です。
――インターリスクでは、食料品やタミフルなど医薬品等の備蓄、或いは事業継続について日系企業に対してどのようにアドバイスを行っているのでしょうか。
一部の企業は、タミフルの備蓄を進めていますが、個人の場合は薬事法等の関係もあってそう簡単には入手できません。しかし、感染予防策は一定水準に達しています。ジャパンクラブでは、日本の水際対策が発表されると同時に帰国問題に取り組んでいます。
インターリスクでは、感染予防と事業継続の普及・啓発活動を行ってきましたが、今後は帰国問題についてどうすれば帰国希望者を円滑に帰国させることができるかについて検討していきます。
――中国やインドネシアでは、このところ、ヒト・ヒト感染の疑いのある事例が報道されていますが、現地ではどのように受け止めているのでしょうか。
中国では今年1月、ヒト・ヒト感染と疑わしい事例が報道されました。北京在住の人たちは、中国でここまで報道するからには実際は相当厳しい局面ではないかと思っている節があります。中国の駐在員から、日本の国際部や総務部に今後どうするべきかについての照会が多く寄せられていると聞きます。
これまでは、「新型インフルエンザって何?」といった状況だったわけです。実は、昨年8月の北京オリンピック前後のことですが、新型インフルエンザが発生して日本人だけ国外退去する事態になっては拙いと感じたある日系企業は、広州で新型インフルエンザに関する説明会を行いました。このとき、現地のトップの人たちでさえ新型インフルエンザについてほとんど何も知識はなかったといいます。
――現地法人と日本本社のマッチングが今一つということですが、そうなると、日本国内の新型インフルエンザ対策は万全か少し気になるところです。
新型インフルエンザは必ず発生するし、自社の従業員も感染するという前提で対策を進めるようお話します。また、様々な局面で対応できるようアドバイスしています。たとえば、保健所への連絡の仕方など実際の手順を踏んで説明します。最終的には人命と企業の存続が大命題ですから、感染予防策の徹底と事業継続の取り組みが両輪です。
――通常のインフルエンザ対策でも、手洗いやうがいの励行、またできるだけ人混みは避け、通勤等のラッシュ時にはマスク着用など、接触感染や飛沫感染をブロックすることが第一です。
感染予防策の実施では、企業として取り組む感染予防策と個人として取り組む感染予防策に大別できますが、1つの対策に傾注することなく、様々な対策を組み合わせて防御するべきであるという考え方です。
会議の際は、相手と一定の距離を取るとか、在宅勤務や電話会議等を活用するとか、大きなコストを掛けることなくコストパフォーマンスを上げる対策を採り入れるようアドバイスします。個人の感染予防策も同様で、コストと伴うものばかりではありません。コストを伴うものとそうでないものを組み合わせ、実効性の高い感染対策を行うことが大切です。
対人の際の接触感染を防止することは、確かに有効です。事業者向けガイドラインでもそう規定されています。しかし、その全てを行うとなると難しいかもしれません。事業者向けのガイドラインでは、外部からの来訪者については入り口で体温を測るなどいくつか計画を設けていますが、規定を作り実践することができるのは時間や人手に余裕があるときです。
パンデミックになると、4割の人が欠勤するわけですから、電話やFAX、Eメール等を最大限に活用する必要があります。契約などどうしても対面でなければならないときに限るべきです。つまり、皆で一緒に行うことです。誰か一人でも足並みの揃わない人がいると、水が漏れてしまいます。周知徹底や教育が大切です。
――インターリスクは、厚生労働省の委員会など公的な場で意見具申していますが、とくに要望したこと、或いは特徴的な議論について話してください。
さきほど感染予防策と事業継続は両輪と申し上げましたが、これは大枠で感染予防策が〈7〉、事業継続が〈3〉という考え方です。感染予防策を徹底すると、感染リスクをコントロールできるという考え方に立っています。
要するに、感染リスクをコントロールできなければ人的被害は甚大であり、しかし感染予防を徹底すると、感染者数と死亡者数は一定低減できるはずという議論でした。
厚生労働省の感染者の推計をベースにすると、従業員数3000人規模の事業所の場合、750人が発症し15人が死亡します。この数値は、感染予防策を推進・徹底するかにより全く違ったものになるはずです。
4人に1人の発症者が出るかどうかは、その取り組みいかんにより異なるわけです。結果的に、あの会社はほとんど大事に至らなかったという企業が出たとしたら、それは万全の準備体制を敷いていたという証しかもしれません。