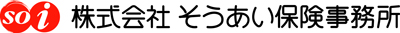『小金井通信』 2025年1月 ◆「月刊ライト」2006年1月号
【アーカイブ】「月刊ライト」2006年1月号(取材・小柳博之)
「ワイド・インタビュー」
小野 尚 金融庁監督局保険課長に聞く
〈プロフィール〉おの・ひさし 1983年4月大蔵省入省。2001年7月金融庁検査局総務課検査企画官、2003年7月検査局調査室長、2004年7月監督局保険課長。1959年10月宮崎県生まれ。東京大学教養学部卒業。
「天災と人災」。この二つの脅威は、私たちの暮らしを虎視眈々とまるでうねりのように狙っている。そして、天災から逃れる術を持たない私たちである。しかし人災は別、予防いかんによってはこのリスクから免れることは可能である。例えば、一昨年(2004年)のようにひとシーズンに10個の台風が上陸する局面ではほとんど成す術はない。
ところが、不注意による列車事故や耐震強度偽装によるマンション建設等の人為ミスは防ぐことができる。昨年明らかになった生保会社の保険金不払い事件は絶対に防止できた。
人災と云うには、お粗末な出来事だった。経営破綻でイメージダウンした生保業界に追い討ちをかけ、契約者不信を一層募らせる事態を招来した。
金融庁監督局の小野尚保険課長に、一連の不適正な保険金不払い問題を含め、①第三分野の責任準備金、②自然災害リスクと異常危険準備金、③根拠法のない共済における契約者保護、④保険のセーフティネットの見直し、⑤個人情報保護法と保険販売、⑥保険の販売・勧誘時の情報提供のあり方など、保険契約者の利便と保護の観点で指摘して頂いた。(取材/構成=編集部・小柳)
――昨年(2005年)の保険業界について振り返って下さい。
小野保険課長: 行政にとって2005年は、利用者利便と利用者保護に重点を置きさまざまな施策に取り組みました。また、さまざまな問題が表面化しました。この全ての事案は結局、利用者利便と利用者保護に関わるものではないかと思います。
具体的には、一昨年末に策定した金融改革プログラムは利用者利便と利用者保護が前面に打ち出されており、この考え方に沿いどういった施策が保険分野において適当かについて検討を重ねました。それは、昨年8月に策定した保険会社向けの総合的な監督指針です。この監督指針では、利用者利便及び利用者保護を明確に打ち出しました。例えば、保険会社の財務の健全確保(財務の健全性)について、また業務の適切性について、さらに財務の健全性や業務の適切性を支える経営理念(ガバナンス)について、の三つを柱に据え監督上の評価項目に組み入れました。
これまで明確なルールがなかった第三分野の責任準備金の積立・事後検証等については、ルールを作る必要があり、こうした趣旨で研究会を立ち上げ、この整備に取り組みました。第三分野商品は、今日相当に普及しています。したがって、利用者が安心して保険に加入できるように、また適切に保険金が支払われるように責任準備金の積立ルールや事後検証ルール等の整備を図る必要があります。
一方、損保分野では、自然災害は世界的に増加してきています。したがって、こうした自然災害に対応できるように、また異常危険準備金がきちんと積み立てられるようにするため、昨年4月から異常危険準備金の積み立てルールを改正し、より厳格化しました。
業務の適切性の観点では、最近の保険商品は複雑で分かりづらいといった指摘や相変わらず苦情やトラブルが多い点に鑑み、保険商品の販売勧誘のあり方に関するルールを整理する必要がありました。このため、「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」を作り、議論を深めました。
さらに、一層の利用者利便の向上と保護を図る観点で、例えば保険商品の価格の弾力化を促進するため、保険料のうち保険数理に基づかない付加保険料部分について商品審査を簡素化する方向性を打ち出しました。
このほか、利用者の満足度の重視も不可欠です。これは、保険会社が個別に取り組まなければならない課題ですが、アンテナを高くし、利用者満足度を把握した上で、商品開発やサービスの向上に繋げることが肝要です。昨年6、7月には、「利用者の満足度向上に向けた懇談会」を設置し、利用者の意見・苦情等を把握するための取り組み、及びそうした意見・苦情等をよりよい金融サービスの提供に反映させるための施策等のあり方について議論して頂きました。
さらに、販売チャネルの多様化の側面から、銀行窓口での保険販売の拡大について進展させました。銀行窓販の拡大は、最終的に利用者利便の拡大に繋がるとの考え方に立ちます。
2005年を概観すると、生・損保を問わず、利用者利便と利用者保護がいかに重要かを再確認した年だったと言えます。また、行政当局としても、そうした利用者利便・保護等に向かい舵を切った年でした。
――昨年は、いわゆる無認可共済について一定の方向性が示されています。
小野保険課長: 無認可共済については、保険業の枠組みの中で少額かつ短期という特性を活かして頂くことになり、現在政省令を詰めているところです。これにより、制度の詳細やその枠組みが決まります。
現行の保険業法は、不特定の者を相手として保険の引き受けを行う保険業が対象です。契約者保護の観点から、保険業法の範囲を見直し特定の者を相手として、保険の引受けを行う事業に原則として保険業法の規定を適用することにしました。
また、任意団体等で特定の者に対して、保険業類似の事業を行う者には従来、法規制や監督官庁がなかったことを踏まえ、一定の事業規模の範囲内で少額かつ短期の保険のみの引き受けを行う事業者について登録制等の新たな規制の枠組みとして、少額短期保険業者を創設しました。
したがって、①制度共済(JA、生協等)、②根拠法のない共済、③保険会社の三つに区分されている保険・共済の枠組みは、2年間の移行期間を経て、「制度共済・企業内共済(労組等)」「少額短期保険業者=登録制」「保険会社=免許制」に改正されます。
この制度の詳細や枠組みの構築には、もう少し時間を要しますが、監督当局として大事だと考えることは、今回の保険業法の改正に至った経緯です。端的に言えば、一部の根拠法のない共済のゆゆしき問題、すなわちマルチ商法的な販売方法など不適切な募集や脆弱な財務基盤等の問題点を十分に踏まえ、監督態勢を整備することです。
また、当面の課題として、新しい保険業法が施行されると、6か月以内に届出を行うことが求められます。この期間内に届出を行わない事業者がいる場合にはどう対応するか。さらにマルチ販売等募集上で問題がある業者が存在する場合の対応、加えて財務上問題がある事業者が存在する場合の対応等が課題です。
共済事業者は今後、保険業法の検査・監督の枠組みに入ってきます。したがって、検査・監督権限を行使する中で、財務・募集問題について監督することになります。また、こうした監督は新たな行政ニーズですから、マンパワーの観点でも適切な人員配置が求められます。この監督に当たっては、基本的に財務局で監督して頂くことになります。
――第三分野の責任準備金の積立・事後検証等について、明確なルールがなかったため、このルール作りに取り組んだとのことですが、この詳細についても触れて下さい。
小野保険課長: 例えば、第三分野は第一分野とは異なり、現段階では統一的な発生率を設定するのが難しい側面を有しています。人によりどのくらい病気になるのか、或いは入院するのか、疾病率に関するデータも十分ではありません。そうした中で、無理に一律標準的な基準を設けると、かえって制度として適切に機能しないおそれがあります。そういった仕組みではなく、将来にわたって第三分野に係る保険金が適切に支払われる責任準備金の積み立てが行われるあり方について、昨年2月から6月まで有識者を中心に突っ込んだ議論を展開しました。
この結果、大別すると四つの柱からなるルールを組み立てました。一つは、毎年将来に備え保険料積立金をきちんと積み立てられているかについて確認する負債十分性テストを定期的に実施・検証し、仮に十分でないときは追加的な積み立てを行うことにしました。
また、昨今問題になっている鳥インフルエンザのように大きな疾病が突発的に発生したとしても、保険金支払いに十分に対応できるよう危険準備金を別途積み立てていますが、この危険準備金が十分に積み立てられているかについては、いわゆるストレステスト(仮想な数値でのテスト)を実施し、十分な支払いが確保されているかについて検証することにしました。
さらに、保険料積立金に係る負債十分性テスト、危険準備金に係るストレステストに加え、その検証の実施状況等を開示(ディスクロージャー)してもらいます。その上で、当局として定期的にテスト等により保険料積立金や危険準備金が十分に積み立てられていることを検証していく考え方です。この四つをきちんと組み合わせて実施していくことにより、保険会社の財務の健全性が確保され、より確実に契約者保護を図ることができると考えます。
一方、自然災害のリスクは、一昨年のように台風が10個も上陸するなど大規模自然災害が増えています。これは、わが国だけの問題ではなく、世界的な傾向ですから、きちんとしたルールを整備する必要がありました。すでに昨年4月から、各社が有する自然災害リスクに応じてより精緻化したリスク計算に基づき、異常危険準備金を積み立てるルールへ移行しています。
このルールについてもう少し詳しくお話しすると、70年に一度の大規模災害にも対応できる異常危険準備金の額を各社が計測し、その目標額に対して計画的に積み増しを行って頂くことにします。一昨年の自然災害でも、十分に異常危険準備金を積み立てていたからこそ、十分な支払いが可能でした。
したがって、損害保険各社は、この異常危険準備金の重要性について十分に認識していらっしゃるはずです。
――セーフティネットの見直しにも着手しましたが、この考え方を要約して下さい。
小野保険課長: 現行の保険業法では、生保も損保も保険の継続性を重視した同じ補償の方式です。原則として、一律に責任準備金の90%を補償する考え方です。これを保険の特性に応じた補償の見直しへ改めることにしました。
損保の自動車保険の場合、他社への乗り換えを促す補償方式を導入しました。破綻後3か月以内は、保険金の100%を補償し、その間に他社への乗り換えを促します。
一方、生保の資金援助等による補償は、契約種類や予定利率など契約内容を勘案し決定します。ちなみに、高予定利率契約の場合は、85~90%程度になる見込みです。また、保険金が運用実績に連動する特別勘定の保険契約については、更正計画において他契約よりも有利な条件を定め100%保全を可能にしました。
――銀行窓販の拡大と2年後のフルライン解禁の方向が示されました。この考え方にも触れて下さい。
小野保険課長: フルラインの解禁については、弊害防止措置が有効に機能するか、或いは銀行での実際の保険募集の実施状況等を検証し、保険契約者等の保護が必要な場合には、その期日を見直すことを前提としています。まず、今後の保険募集の実施状況や弊害防止措置の実効性についてモニタリングしていくことが重要です。
ただし、今後のあるべき姿については、自ずと得意分野、不得意分野が決まってくると思っています。例えば、死亡保険の場合には、お客の潜在的なニーズを掘り起こす必要があり、時間と手間が掛かります。そういった保険が本当に銀行販売に適しているのか。また自動車保険は専門的な知識が必要ですから、銀行窓口で適切な助言ができるかといった問題があるかもしれません。相当なマンパワーを要しますから、費用対効果でどこまでやるべきかについて各々経営判断を求められることになるでしょう。銀行窓販にふさわしいか否かで、自ずと棲み分けができてくるのではないかと思います。従来型販売のほうが、効率のよい分野もあるはずです。
――個人情報保護法が昨年4月に施行されました。この取り組みに際しては、保険会社も保険代理店等も相当に苦慮したようです。
小野保険課長: 保険分野は、医療情報等の極めてセンシティブな情報を扱っています。また保険代理店や営業職員は、営業のために個人情報を事務所や営業所の外に持ち歩かなければなりません。したがって、個人情報のより適切かつ厳格な取り扱いが必要になります。金融庁の個人情報ガイドラインや実務指針では、個人データの漏洩等について安全管理措置を講じることを義務付けています。したがって、保険会社は、それぞれ安全管理のための基本方針や社内規定を適切に講じる必要があります。
また、保険会社は個人データを業者に委託するケースがあります。委託業者に対する必要かつ適切な監督が求められます。さらに、保険会社は保険代理店との間で顧客情報の取り扱い規定を締結し、保険代理店に対して必要かつ適切な監督を行うことが求められます。これは、営業職員についても同様です。個人情報の安全管理措置が図られるよう必要な監督を行うことを求めています。個人データの非開示契約を募集人と締結し研修等を行い、個人情報の適切な取り扱いの確保を求めています。
このような経過措置を各社が講じることにより、各保険会社において一定の対応が図られると考えています。しかし、残念ながら個人情報保護法施行後も、個人情報の漏洩や紛失が一定程度発生している現状に鑑みると、ルールや規定を作成すればそれでよいわけではなく、そのルール等が実効性のあるものになる措置を講じることが必要です。
そして、何より大切なことは、募集人や保険代理店の一人ひとりが自分たちはお客の極めて重要な情報を扱っているという自覚を、要するにプロ意識を持って頂きたいと思います。一人ひとりに自覚があり、きちんと規定が整備され、実効性が確保されると、個人情報の漏洩は相当程度防止できるはずです。
――金融庁は昨年10月末、保険金等支払い管理態勢の再点検及び不払い事案に係る再検証の結果について公表しています。この点にも触れて下さい。
小野保険課長: 極めて遺憾なことですが、昨年の大きな事件として生保における不適切な保険金不払い問題がありました。この原因について分析すると、まず販売勧誘のあり方として、募集人が契約者に対し告知義務等の重要事項の説明を行っていない、不告知を教唆する等の問題がありました。
また、支払い管理態勢として、適切な査定基準に基づき、支払うべきものについて支払うことは保険会社の基本的な機能、いわば1丁目1番地です。これをやっていなかったとすれば、まさに大問題です。二重、三重のチェック態勢を敷き、請求を受けた保険金を支払うことが適当かについて慎重に検討を行い、チェックする態勢を構築しなければならないわけです。
そして、苦情処理です。今般の不適切な保険金の不払い問題でも、元々保険金の不払いについてお客から苦情が寄せられているにもかかわらず、また苦情が増えているにもかかわらず、経営陣はこれを見逃しました。お客からの苦情という重要なシグナルを見逃したことで、問題は大きくなりました。全ての保険会社は、この問題をきちんと受け止め、苦情がいかに重要なシグナルかについて認識を新たにして頂きたいと思います。
最後は、やはりガバナンスです。きちんとした経営管理態勢を敷き、支払い管理態勢は大丈夫か、苦情処理は機能しているか、募集管理は適切に行われているかについてチェックし、責任を持って経営管理に当たることが経営陣です。これができなかったことが、今回の最大の問題点です。
一方、問題の性質は全く異なりますが、損害保険業界でも付随的な保険金についての支払い漏れがありました。主契約の部分については、交通事故でけがをしたときや、クルマが破損したときの保険金は支払われているものの、その特約部分について契約者が、自らがどういう特約に入っているのかが分からず、保険会社もそれを確認できなかったため請求を行わず、その結果として、本来支払われなければならないものが支払われなかった案件が発生しました。
生保と違い、お客が支払いを請求したにもかかわらず、支払わなかったわけではありません。しかし、当然支払うべき保険金を支払っておらず、やはり問題です。この損保の付随的な保険金の支払い漏れ問題について分析すると、特約が複雑でお客がよく分からないという側面が浮かび上がってきました。
要するに、販売勧誘時におけるお客に対する説明が不十分だったと指摘できます。また、お客から主契約についての保険金の請求があったとき、お客に対し「こういう付随的な特約がついています」と確認できる事務管理、システム対応ができていませんでした。これは、支払い管理態勢に問題があったことにほかなりません。
そもそも主契約に加え、さまざまな付随的な特約が付く商品を開発する以上、商品として機能するかについて、販売後にきちんと保険金が支払われるような態勢になっているかについて、バックオフィスの体制やシステム対応についても検証する必要があります。仮に、こうした検証なくして販売に至っているとしたら、商品開発態勢に問題があったと言わざるを得ません。
こうした事態を真摯に受け止め、各保険会社では何を置いても利用者利便と利用者保護を推し進めていかなければなりません。
――販売勧誘時の情報提供のあり方についても触れて下さい。
小野保険課長: 販売勧誘に関する苦情は依然として多いわけですが、これは保険商品の多様化、複雑化により、消費者は商品内容が理解しづらくなっているからです。この点を踏まえ、野村修也中央大学教授に座長になって頂き、昨年4月法律の専門家、弁護士、消費者代表、業界代表による「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」を立ち上げ検討に着手。その第一弾として7月、『明瞭かつ丁寧に説明されるべき重要事項及び顧客への説明態様のあり方』について論点整理を行い公表しました。
論点整理では、お客にとってとくに説明すべき重要事項を明確化しようと試みました。すなわち、まず顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報、「契約概要」が必要と考えました。また、保険会社が顧客に対し注意を喚起する情報(クーリングオフや告知、いつから保険カバーになるか)など『注意喚起情報』も必要と盛り込み、この二つの情報をA3両面程度のサイズにコンパクトにまとめました。この枠組みについては、法令等で定め細目について業界の自主ガイドラインで対処することにしました。また、消費者が保険商品を購入するに当たって、どのような点に留意したらよいかについてまとめた『バイヤーズガイド(購入者手引き)』も作成することにしました。現在、この準備を進めています。
――話を締め括って下さい。
小野保険課長: 金融庁は、金融サービス利用者相談室を昨年7月中旬に開設しました。金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を金融行政に有効に活用することを目的としています。生保における不適切な不払いも、実は一昨年秋に当局に寄せられた苦情が端緒となっています。こうした側面から問題解明に繋がりました。私自身としても、今後とも国民の皆さんのご相談やご意見を十分に踏まえ、監督行政に活かしていきたいと思っています。金融庁としても、よりアンテナを高くして監督行政を行う必要があると感じています。
さきほどの話に戻りますが、お客から保険料を預かっているのですから、適時適切に保険金を支払うことは保険業の根幹に関わることです。この基本だけは、きちんと抑えて頂かなければなりません。金融庁としても、今般の保険金等の不適切な不払い、付随的な保険金の支払い漏れという重大な問題を招いた原因の分析結果を踏まえ、保険会社向けの総合的な監督指針の改訂を行い、適時適切な保険金支払いを行い得る、また苦情をきちんと汲み上げられる態勢整備を求めていきたいと思っています。繰り返しますが、個々の会社においてはお客からの苦情や相談をきちんと受け止め、適切に処理することを心掛けて頂きたいと思います。また、国民の皆さんの不信を払拭するためにも、生・損保の各協会の苦情相談や紛争処理態勢の一層の充実を図って頂きたいと思っています。