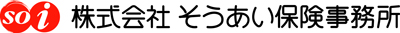『小金井通信』 2024年12月 金融審議会総会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第6回)
●損害保険市場における保険金不正請求事案や保険料調整行為事案の発生を受け、金融庁が設けた、金融審議会「損害保険業等に関する制度等WG」は、12月13日の第6回会合で「損害保険市場・損害保険業界の現状及び保険市場に対する信頼の回復と健全な発展に向けた課題」について論議し、『「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書』を取りまとめた
(取材・小柳博之)
金融庁の金融審議会「損害保険業等に関する制度等WG」(座長・洲崎博史同志社大学大学院司法研究科教授)は12月13日10時から中央合同庁舎第7号館9階905B共用会議室及びオンラインで第6回会合を開催。会合の模様をYouTubeでライブ配信した。
洲崎座長は、前回論議した内容を事務局が修文・加筆した報告書案について事務局に説明を求めたのち、討議に入った。
金融庁監督局は、損害保険市場における保険金不正請求事案や保険料調整行為事案の発生を受け、今年3月に「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」を設け検討を行った。
金融担当大臣は、今夏8月の金融審議会総会の席上、「昨今の損害保険業界における保険金不正請求事案や保険料調整行為事案などを踏まえ顧客本位の業務運営や健全な競争環境を実現することにより、保険市場に対する信頼の確保と健全な発展を図るために必要な方策について検討を行う」と諮問した。
金融庁企画市場室はこれを受け、金融審議会に「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」を設置。9月27日の初会合から6回に及ぶ議論を経て同日、①大規模乗合代理店に関する規制のあり方、②保険仲立人の活用促進に向けた施策、③損害保険会社における火災保険の赤字構造等に関する成案を得た。
金融庁が行った実態調査では、大手損保4社の企業内代理店は9530社。各社ごとの収入保険料上位300社に対する調査では、企業内代理店は256社だった。『「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書』では、「企業内代理店は、保険業以外の事業を営む企業と人的・資本的に密接な関係を有し、主にグループ企業向けの火災保険や賠責保険等の契約や、福利厚生の一環として、グループ企業の従業員に係る保険契約を取り扱っている。しかし、その立場は不明確。実務能力の乏しい保険代理店でも一定の手数料収入が得られ、保険代理店として存続できる。企業内代理店に支払われる手数料は、保険料の実質的な割引になっている」と指摘し、特定契約比率規制の見直しを示唆した。
具体的には、保険料の実質的な割引・割り戻しの防止及び損害保険代理店の自立の促進の観点から問題がない場合、同規制の適用除外の枠組みを設けると規定。また、保険仲立人(ブローカー)への特定契約比率の適用については、保険仲立人が顧客から手数料を受領する場合、顧客から委託を受ける保険仲立人の立場が明確になること、また同手数料の水準にかかわらず、保険料が一定であることを踏まえ適用除外と規定した。
わが国におけるブローカー制度は、保険市場の自由化と国際化に向けた健全な競争促進の担い手として、1995年の保険業法改正の際に導入された。しかし、高い参入障壁により、一部企業保険分野の活用にとどまっており、その形骸化が指摘されていた。今回、同ワーキング・グループがその活用促進に踏み込んだことで、保険仲立人は30年の時空を超えて市場にランディングする。
同報告書(案)は、Ⅰ.はじめに Ⅱ.顧客本位の業務運営の徹底(1.大規模乗合代理店に対する体制整備義務の強化等 2.乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保 3.保険代理店に対する保険会社による適切な管理・指導等の実効性の確保等 4.損害保険分野における自主規制のあり方の整理) Ⅲ.健全な環境の実現(1.保険仲立人の活用促進 2.保険会社による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止 3.企業内代理店のあり方の見直し 4.火災保険の赤字構造の改善等) Ⅳ.おわりに、の4章立て。
事務局は、Ⅳ.おわりに、「なお、本ワーキング・グループを開催する中でも、保険会社や保険代理店における情報漏えい事案が相次いで認められていることは誠に遺憾である。現在、当局において、事実関係の把握、真因分析等の検証が実施されているところであるが、今後、この検証を通じて明らかになる内容を踏まえて、早急に必要な措置を講ずるべきである。
今般の保険金不正請求事案と保険料調整行為事案に係る業務改善命令の対象となった損 害保険会社各社においては、適切なガバナンス機能を発揮させ、業務改善計画を着実に履行すべきことは当然である。また、損害保険会社は、顧客本位の業務運営に関する原則や改正金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づく顧客等の最善の利益を勘案して誠実かつ公正に業務を遂行する義務を改めて認識した上で、適切なガバナンス態勢を構築するほか、これらの趣旨に反する古い慣習と決別すべきである」と明記した。
オブザーバーの平賀暁保険仲立人協会理事長は、前回会合の質疑で事務局に対し「保険仲立人は顧客に対して、手数料を、保険会社から全額受領するか、顧客から全額受領するか、顧客と保険会社双方から受領するかをあらかじめ説明することが適切である。また、保険会社から手数料を受領する場合、保険仲立人は顧客に対して、保険会社から受領する手数料の額は保険料に占める割合等をあらかじめ開示することが適切であると記されている。これは全てを総称し言っているのか、或いは双方取りを踏まえ、三者で調整した上で決定する旨を記載しているのか、いずれでしょうか。手数料の受領先及び金額についてであれば、双方取りを前提として書かれているようにも思えますが、この書きぶりについてもご検討を頂きたい。おわりに、の中に、保険仲立人の活用についても触れて頂きたい」と要請した。
これに対して、最終報告書案は、「手数料の受領先及び金額については、その受領方法に応じて、保険仲立人と顧客、保険仲立人と保険会社のそれぞれにおいて調整した上で決定することが考えられる。
もっとも、顧客からも手数料を受領できるようにした場合、保険仲立人が、顧客と保険会社の双方から手数料を受領することも考えられるが、顧客が手数料の総額を把握していなければ、必要以上の保険調達コストを負わされかねないため、顧客の利益が害されないよう一定の措置を講ずるべきである。
具体的には、保険仲立人は顧客に対して、手数料を、保険会社から全額受領するか、顧客から全額受領するか、顧客と保険会社の双方から受領するかをあらかじめ説明することが適切である。また、保険会社から手数料を受領する場合、保険仲立人は、顧客に対して保険会社から受領する手数料の額又は保険料に占める割合等をあらかじめ開示することが適切である。なお、顧客と保険会社の双方から受領する場合は、顧客が必要以上のコストを負わないようにするため、保険仲立人は、保険会社に対しても顧客から受領する手数料の額を開示することが望ましい。
ただし、このように一定の顧客保護の措置を講じたとしても、個人顧客との間には情報の非対称性等から生じる交渉力の優位性が総じて残りやすいことを踏まえると、顧客からも手数料を受領できるように見直しを行うのは、まずは企業向け保険のみを対象とすることが適切である。その上で、今後、保険仲立人の参入による少額・リテール市場の活性化も想定されることや、顧客に対する一層の誠実義務が果たされ顧客保護意識が向上していくと期待されることを踏まえると、中期的には、個人顧客も対象から排除しない方向で検討を継続することが適切である」と規定した。
また、Ⅳ.おわりに、の中に「保険仲立人においては、今後、健全な競争環境の実現の観点から講じられる諸施策を通じて、様々な形態での便宜供与が解消され、保険商品・サービスの差別化や損害保険会社の参入が促進されれば、顧客がより多くの損害保険会社から適切な保険商品を選ぶことができるようになることが期待されるが、そうした環境下では、保険仲立人が果たす役割への期待が一層高まっていくものと考えられる。本報告で示した一連の施策を通じて新たな実務が形成されていく中で、保険仲立人の層がさらに厚くなり、我が国の保険市場におけるプレゼンスが高まっていくことが望まれる。
損害保険会社、損害保険代理店、保険仲立人といった損害保険市場における各主体において、本報告書の内容を前向きに受け止め、保険市場に対する信頼の確保と健全な発展に向けた取り組みが進められることを、強く期待したい」と盛り込み、保険仲立人の活用促進による損害保険市場の健全性確保と市場活性化に期待感を寄せた。
洲崎座長は、「今回のワーキング・グループは9月終わりから始まり、3か月弱のタイトなスケジュールの中で事務局の尽力と踏ん張りでようやくゴールに近づいてきた。事務強のご尽力に敬意を表する。各委員には、真摯で熱心な議論を頂いた。少数意見も採り入れており、座長としても、晴らしい報告書案を取りまとめることができたと思う。特定の立場に立った党派的な主張ではなく、いずれも耳を傾けるべき意見だったと思われる。本報告書はエポックメーキングな内容が盛り込まれており、今提言が実現すると損害保険の実務慣行を大きく是正できる。長年にわたる悪しき実務慣行にメスを入れられる貴重な機会である。当局をはじめ、損保会社、保険代理店の方たちや、その背後にいる企業の方々には、この報告書に書かれていることが実現できる日までご協力を頂きたい。本報告書案は大筋で賛同を頂けたと思われる」と感謝を表明するとともに、同日の意見や表現の平仄を合わせる精査と報告書公表の取り扱いについて一任を取り付けた。
由布志行企画市場局長は、「本ワーキング・グループは、これまで6回にわたり洲崎座長はじめ、メンバーの皆さまに精力的にご検討頂いた。厚く御礼申し上げる。メンバーの中には、本年3月の監督局に設置した有識者会議から継続してご参加して頂いた方もいらっしゃる。重ねてお礼を申し上げる。
事務局では今後、報告書に示された内容に沿って法律改正を含めた制度整備等に取り組みたい。法律政令、内閣府令、監督指針、自主ガイドライン、協会等の取り組みまで含めると、総体として大きな改正になる。こうしたプロセスで、再びご助言を賜るかもしれない。その際にはよろしくお願いしたい」と議事を締め括った。
WGメンバーは13名。上杉東京経済大学現代法学部教授/大村三浦法律事務所弁護士/沖野東京大学大学院法学政治学研究科教授/小畑一般社団法人日本経済団体連合会経済基盤本部長/片山日本労働組合総連合会総合政策推進局経済・社会政策局長/神作学習院大学法学部教授/小林ANAホールディングス社外取締役/嶋寺 基大江橋法律事務所弁護士/滝沢デロイト・トーマツ・コンサルティング執行役員/中出早稲田大学商学学術院教授/松井東京大学大学院法学政治学研究科教授/柳瀬慶應義塾大学商学部教授/山下京都大学大学院法学研究科教授。